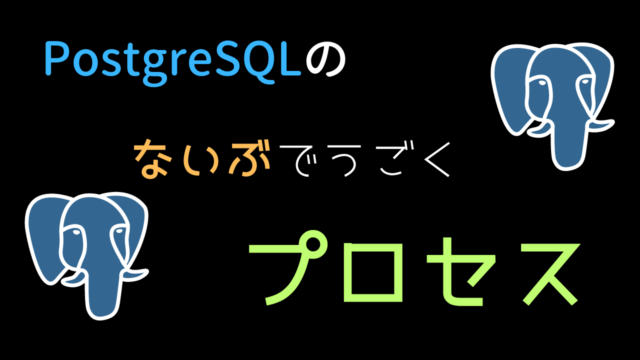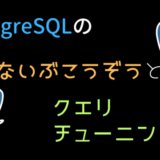はじめに
この記事では、
PostgreSQLのパフォーマンスチューニングの際、
アプリケーションエンジニアが理解しておくと現場で役に立ちそうな部分に絞って、
まとめました。
リライトしたのでこちらの記事をご覧ください。
よくあるパラメータチューニング例をまとめています。
 パラメータチューニング〜PostgreSQLのきほん〜
パラメータチューニング〜PostgreSQLのきほん〜
他にもデータベース関連の現場で役立つネタを
まとめ記事にしているので
こちらも是非ご覧ください!!
 初めてデータベースを触る方に向けて〜新人プログラマー時代の自分に伝えたいこと〜
初めてデータベースを触る方に向けて〜新人プログラマー時代の自分に伝えたいこと〜 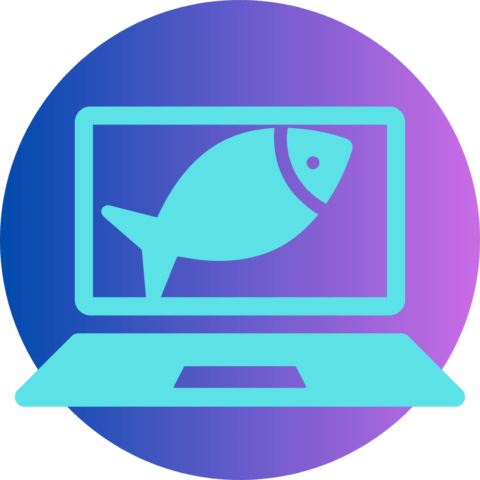 釣りキチプログラマー翔平の備忘録
釣りキチプログラマー翔平の備忘録